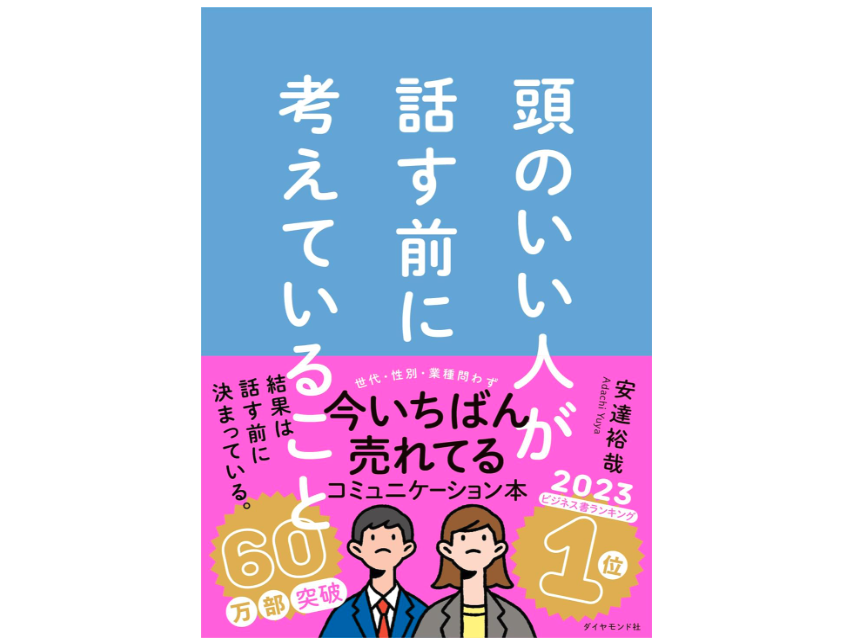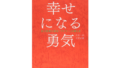頭のいい人が話す前に考えていること 安達 裕哉
発行:ダイヤモンド社
ページ数:338ページ
第1部 頭のいい人が話す前に考えていること
7つの黄金法則
①とにかく反応するな
感情が高ぶったときに下される判断は、しばしば誤りです。
感情に流されることなく、まずは冷静になって考える時間を持つことが重要です。
すぐに反応するのではなく、考えを練ることで最善の行動を選べます。
②頭のよさは、他人が決める
頭の良さは自己判断するものではなく、他者からどう見られるかによります。
周囲からの認識が、あなたの知性の評価を形成します。
③人はちゃんと考えてくれる人を信頼する
他者からの信頼を得るには、単に知識を誇示するのではなく、それを他人のために使うことが大切です。
他人の話に耳を傾け、本当に役立つ情報を提供することで信頼関係を築くことができます。
④人と闘うな、課題と闘え
議論は勝ち負けを競う場ではなく、共通の問題解決に向けて進むべきです。
本質的な課題に注目し、対話を通じて解決策を探求することが肝要です。
⑤伝わらないのは、話し方ではなく考えが足りないせい
伝わるコミュニケーションは、単に型にはまったプレゼンではなく、深い思考と質問に基づいて行うべきです。
質の高い思考が、相手にとって価値ある情報となります。
⑥知識はだれかのために浸かって初めて知性となる
知識を有効活用するためには、それを自慢するのではなく、実際に誰かの役に立つように使うことです。
これにより、知性が評価されます。
⑦承認欲求を満たす側に回れ
コミュニケーションで成功するには、自分の承認欲求を抑え、他人のそれを満たすことに焦点を当てるべきです。
これにより、信頼と尊敬を獲得しやすくなります。
第2部 一気に頭のいい人になれる思考の深め方
5つの思考法
①客観視の思考法
効果的な議論を行うためには、特に以下の二つのポイントが重要です。
・異なる意見の探求 – 自分の意見に対立する視点も積極的に調査すること。これにより、自分の考えに潜む確証バイアスに気づき、より包括的な理解を得ることができます。
・データの活用 – 信頼できる統計データを収集し、分析することで、議論に客観性と説得力を加える。
コミュニケーションにおいては、使用する言葉の選択が重要です。
賢い人は、言葉が持つ意味が相手にどのように受け取られるかを深く考慮し、意味の曖昧さを避けるために用語の定義を明確にします。
これにより、誤解のない、明確なコミュニケーションが可能となります。
浅い思考の特徴
根拠が薄い: 要点が少なく、信頼性の低い情報に依存する。
定義を考慮しない: 言葉の意味を考慮せず、誤解を招く可能性がある。
背景の理解がない: 物事の成り立ちを知ることで、独自のアイデアや議論が深まる。
②整理の思考法
理解するという行為は本質的に「分類」と「整理」することです。
理解できない状態とは、情報や考えを適切に分けて整理できていない状態を意味します。
効果的にコミュニケーションを取る際、特に結論を求められる状況では、相手が最も聞きたい情報から提供することが重要です。
これは、自分の伝えたいことを優先するのではなく、聞き手の関心に応じて情報を整理し提供することを促しています。
話し始める前に、どのような反応や理解を望んでいるかを明確に考え、
相手の興味や期待に応じた「聞くスイッチ」を意識的に押すことが、コミュニケーションを円滑にする鍵です。
また、「自分の意見を持つ」というプロセスは、客観的事実に基づいてスタートし、
適切な根拠を集めることで、他人も納得できる形に整えることです。
結論から話す: 聞き手が最も聞きたい情報を最初に提供する。
事実と意見の分離: 反射的な反応を避け、検証可能な事実と個人的な意見を区別する。
③傾聴の思考法
話を聞ける人は、相手の言葉を正確に理解しようと努める人です。
これに対し、聞けない人は表面的には聞いているように見えても、
実際には自分のフィルターを通して情報を選択的に受け取ります。
人間は、知らず知らずのうちに、自分に都合の良い解釈をしてしまう傾向があります。
話を聞ける人は、相手の発言に対して余計なコメントを挟まず、
相手が何を伝えようとしているのかを深く理解しようとします。
このような聞き方をされると、話している側は自分の意見が正しく受け止められていると感じます。
相談に乗る際も、相手がどのような解決を望んでいるのかを聞き出し、
その意向を支持することが大切です。自らの解決策やアドバイスを押し付けるのではなく、
相手のニーズに耳を傾け、その要望に応じることが、効果的なコミュニケーションへと繋がります
有効な傾聴の態度
・肯定も否定もしない。
・相手を評価しない。
・無闇に意見を述べない。
・沈黙を保ちながら聞く。
・好奇心を活用する。
④質問の思考法
質問をする前に、相手の視点を理解し、具体的な仮説を立ててから質問することが重要です。
「どう思う?」という漠然とした質問よりも、はるかに具体的で意味のある回答を引き出すことができます。
相手の立場を考慮し、仮説に基づいて質問することで、対話の質を向上させることが可能です。
質問技術の改善
・直面した課題に対する対応を問う。
・仮定に基づくシナリオを提示し、それに対する反応を探る。
・具体的な行動とその結果に焦点を当てる。
⑤言語化の思考法
優秀な人は、自分のアウトプットがどのようにして形成されたのかを説明する能力を持っています。
彼らは、アイデアの発端、使用した方法論、そしてその思考過程を明確に言語化できます。
言語化することなく、継続的に高品質の成果を生み出すことは難しいです。
思考のクオリティは言語化のクオリティに直結し、
その言語化のクオリティが最終的なアウトプットのクオリティを左右します。
高品質のアウトプットは人々の心を動かし、それが行動につながります。
言い換えれば、深く考えることは、影響力のある成果を創出することに等しいです。
さらに、人間は名前のないものについて深く考えることが難しいため、
ネーミングは思考を刺激する出発点になります。
何か新しい概念を発見したら、それに名前を付けることで、思考がより具体的で質の高いものになります。
言語化の工夫
・コミュニケーションコストを意識し、効果的な言語表現を追求する。
・具体的なネーミングで思考を明確化する。
・感情を表す一般的な表現を避け、具体的な表現を用いる。