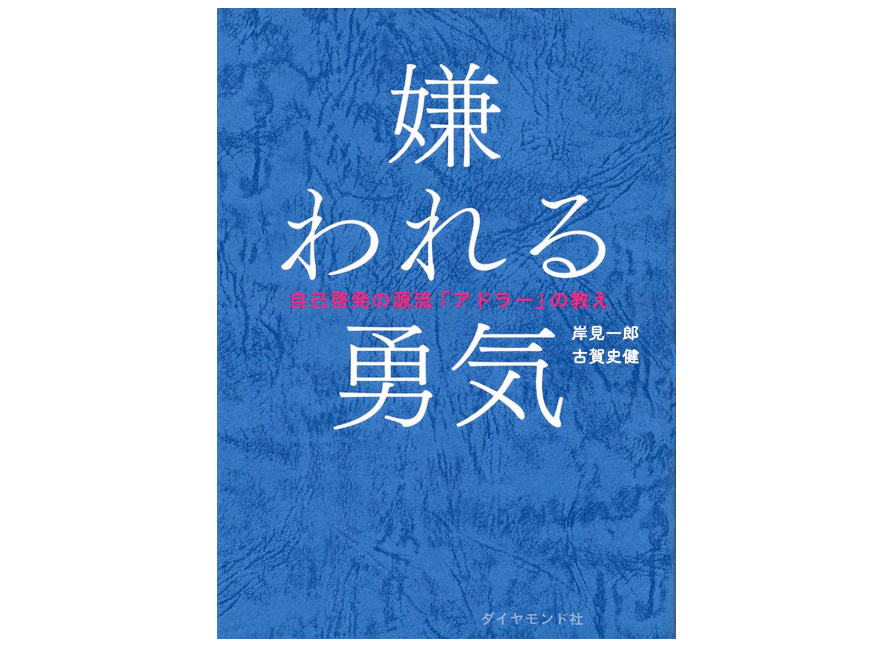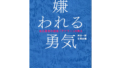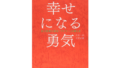嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見 一郎、古賀 史健
第三夜 他者の課題を切り捨てる
承認欲求の落とし穴
アドラー心理学は、承認欲求を否定しており、承認を追求することは避けるべきです。
例えば、掃除をして誰も褒めてくれなかったとしても、
掃除をした理由が承認を得るためだけであるならば、その動機は問題があります。
これは、「褒められることが目的で掃除をし、褒められなければもうしない」という考えに繋がりますが、これは理にかなっていないでしょう。
私たちは他者の期待を満たすためではなく、自己の価値観や目標に従って生きるべきです。他人の期待を満たす必要はありません。
他人の目や評価を気にしすぎると、結局は他人の人生を生きることになり、自分自身の人生から遠ざかってしまいます。
他人を変えることはできませんし、他者の期待に応えようとするほど、生きづらさを感じるようになります。
自己の内面と価値に焦点を当て、自分自身のために行動することが、より健全で満足のいく生活へと繋がります。
課題の分離の重要性
アドラー心理学では、問題に対処する際に「これは誰の課題か?」と問い、
自分の課題と他人の課題を明確に区別することが推奨されます。
例えば、勉強をしない子供に対して指示を出す親や、
依頼されていないのに他人にアドバイスをする人々は、実は他人の課題に過度に関与しています。
これにより、アドバイスを受ける側は不快感を覚え、「放っておいてほしい」と感じることが多いです。
対人関係での多くのトラブルは、他人の課題に無理やり介入すること、
または自分の課題に他人が介入してくることから生じます。
では、どのようにして自分と他人の課題を見分ければ良いのでしょうか?
考え方は、「その決断の結果を最終的に誰が受け入れるか?」と自問することです。
たとえば、子供が勉強しない問題について、完全に放置すべきかと言うとそうではありません。
重要なのは、子供にその問題が彼自身の課題であると認識させること、
そして彼が勉強を始めることを望んだときに支援を提供することを伝えることです。
子供が自発的に勉強を始めるまで、不必要に干渉するべきではありません。
このアプローチを表すイギリスのことわざ
「馬を水辺に連れて行けるが、水を飲ませることはできない」は、課題の分離を象徴しています。
最終的に変化を遂げることができるのは、その人自身だけなのです。
嫌われる勇気
誰もが意図的に嫌われようとは思いませんが、すべての人から好かれることは不可能です。
しばしば、人々は他人からの評価を恐れ、嫌われることを避けるために、
本意ではない仕事や約束を引き受けがちです。
しかし、他人があなたを好むかどうかは、
実は「相手の課題」であり、あなたのコントロールを超えています。
他者からの承認を求めずに済むようになると、本当に自分の望む生活を送ることが可能になります。
これには、他者から嫌われるリスクを受け入れる勇気が必要です。
まず自分自身を変えることから始めるべきです。
それによって、相手があなたに対して感じることが変わるかもしれませんし、
変わらないかもしれませんが、それは「相手の課題」です。
自分と他人の課題を明確に分け、相手の感情や反応に縛られずに生きることができれば、
真の自由を手に入れることができ、嫌われる勇気も自然と身につくでしょう。
第四夜 世界の中心はどこにあるか
共同体感覚とは
アドラー心理学では、対人関係を形成する基盤として「課題の分離」を考えますが、
その究極の目的は「共同体感覚」にあります。
この共同体感覚とは、他人を単なる知人ではなく、仲間として受け入れ、自分自身がその中に居場所を見つける感覚です。
共同体感覚を培うための鍵は、自己に対する執着を減らし、他者への関心を高めることにあります。
多くの自己中心的な人々は、世界が自分を中心に回っていると錯覚していますが、
それはしばしば自分自身の課題と他人の課題の区別がついておらず、承認欲求に捕らわれているためです。
世界地図を見ると、どの国も地図の中心に描かれることが一般的ですが、
地球儀を見ると、中心は決まってません。見る位置によって変わります。
これは人間社会においても同じで、誰もが共同体の一員であり、誰一人として絶対的な中心ではありません。
共同体感覚では、「この人に何を与えることができるか?」という考えが重要です。
他者との繋がりを深め、自己中心的な視点から脱却することで、真の対人関係の豊かさを実感することができます。
このように、自分と他者への理解を深めることで、共同体内での自分の役割を見つけ、より充実した人間関係を築くことが可能となります。
叱ってはいけない、褒めてもいけない
アドラー心理学では、他人とのコミュニケーション、
特に子育てにおいて、叱ることも褒めることも推奨されません。
なぜなら、これらの行為がしばしば「上下関係」を生み出し、劣等感や競争心を助長するからです。
褒める行為が含む「上からの評価」という側面は、しばしば受け取る側に不快感を与えることがあります。
これは、褒める人が能力があると自己判断し、褒められる人を劣っていると見なす際に生じる関係性です。
このような「縦の関係」ではなく、「横の関係」を築くことが大切です。
評価するのではなく、相手に感謝する姿勢を持つことが、健全な人間関係の基礎を形成します。
人は自己の価値を認識し、自らが他者に何かしらの貢献をしていると感じるときにのみ、
本当の意味で自信や勇気を持つことができます。
「何をしているか」ではなく、「存在そのものに感謝する」ことが重要です。
たとえば、病を抱えてる方で「自分は何も貢献していない」と思う人がいるかもしれませんが、
その人を愛する家族にとっては、その存在自体が大きな意味を持ち、深い感謝の対象となります。
自分がこの世に存在するだけで、家族や友人にとって価値があると実感できたとき、
人は自己の価値を感じ、新たな勇気を見いだすことができるのです。
第五夜 「いま、ここ」を真剣に生きる
幸福の本質
幸福は、現在の瞬間から感じることができます。これは、他人との平等な関係を築き、感謝の気持ちを持つことから生じるものです。
「誰かのために何かをする」という意識が、自己の価値を感じさせ、充実感をもたらします。
その貢献は、必ずしも目に見える形である必要はありません。
他人から直接感謝されなくても、自分が「誰かの役に立てた」と感じることができれば、それが自己の満足につながります。
したがって、真の幸福は、「貢献感」に他なりません。
自分が他者との関係の中でどれだけ価値ある存在であるかを認識することが、幸福への鍵となるのです。
人生の捉え方
人生を一つの登山に例える人は、人生を一本の線として見ています。
この視点では、多くの瞬間が単なる「通過点」として扱われがちです。
例えば、「いつかお金持ちになる」とか「今は忙しいけれども、将来落ち着いたら」といった考え方がそれに当たります。
しかし、実際には、人生は連続する一瞬一瞬から成り立っています。
それゆえに、私たちは「いま、この瞬間」にしか存在し、生きることができません。
よって、私たちは現在の瞬間をもっと深く、真剣に生きるべきです。
世界は他人が変えてくれるのを待つのではなく、自分自身の行動によって変わります。
アドラー心理学は、他者を変えるものではなく、自身を変えるための心理学です。
この視点から、自分自身の人生を積極的に生きることが、真の成長と変化をもたらすのです。