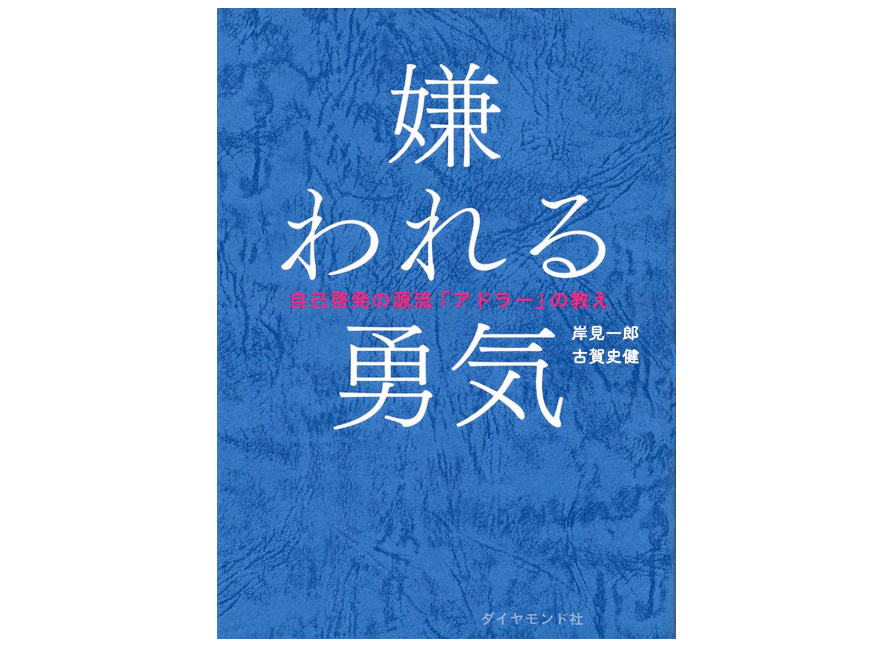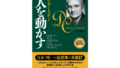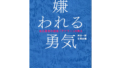嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見 一郎、古賀 史健
発行:ダイヤモンド社
ページ数:296ページ
第一夜 トラウマを否定せよ
「原因論」から「目的論」への視点転換
アドラー心理学は過去の原因を重視するよりも、現在の目的に焦点を当て、トラウマの概念を否定しています。
例:引きこもり
この男性は外に出たいと願っており、できれば仕事をしたいと考えています。
しかし、外出しようとすると動悸が始まり、手足が震える状態になります。
これは「過去のトラウマによる」と一般的には考えがちですが、アドラー心理学では異なるアプローチを取ります。
「外に出たくない」という本人の深層的な意志が先にあり、
「不安」という感情はその目的を達成するための手段に過ぎないと解釈します。
この視点では、不安や恐怖は自己防衛の一環として自ら生み出された感情であると見なされます。
引きこもりが続くと、周囲は心配し、その人に対して丁寧な扱いをすることが多くなります。
外に出た場合、特別な存在から一般の人々の一員になり、注目されなくなる恐れがあります。
見劣りすることを避け、特別視される状態を保つために、「外に出ない」という選択をしているのです。
例: 店員に怒鳴る人
カフェで本を読んでいる最中、偶然ウェイターが通りかかり、
新しい服にコーヒーをこぼす事故が起こった。
この時、購入したばかりの服だったこともあり、強い感情が湧き上がり、
ウェイターに向かって声を大にして怒鳴りつけた。一見、事故が直接の原因で怒ったように見える。
しかし、この行動を目的論的視点から見ると、怒鳴るという「行動」が目的であり、
この目的を達成するために怒りという感情が利用された。
つまり、怒鳴ることでウェイターを圧倒し、自分の望む対応を引き出そうとした。
怒りは単なる手段であり、一種の「道具」として用いられたのである。
怒りを表現することなく、冷静に事情を説明していれば、ウェイターも謝罪し、適切な対応を取ってくれたかもしれない。
しかし、その過程を省略し、より迅速に結果を得るために、怒りという感情を選択して行動に移した。
この事例は、私たちがどのように自己の目的に基づいて感情や行動を選択しているかを示している。
人が変化を避ける理由
多くの人々が自ら「変わらない」という選択をしています。
たとえ現在の状況に不満があっても、それを変えることなく耐え続けるのは、
変化しないことに安心を見出しているからです。
例えば、職場が辛い場合や恋人との価値観の不一致など、これらはすぐに解決可能な問題ですが、
多くの人はその一歩を踏み出さない選択をします。
目的論に基づくと、このように現状を維持する選択は、
「変化することの不安」を避け、「現状の安定」を優先するためです。
これは、「幸せになる勇気」を持つこと、すなわち現状から脱却する勇気が不足しているために起こります。
私たちの多くは過去の経験や現在の環境に囚われがちですが
、目的論はこれらが私たちの未来に直接的な影響を与えるわけではないと教えています。
むしろ、それは「今、この瞬間」に私たちがどのような選択をするかによって左右されるのです。
変化は自己の意志によってのみ可能となるため、自身の状況を改善するかどうかは、完全に個人の決断にかかっています。
人生は「現在の選択」によって形作られる
目的論の核心は、「人はいつでも変化することができる」という信念にあります。
もし変化が見られない場合、それは自分自身で「変わらない」と決めているからです。
これは、基本的に「幸せになる勇気」、すなわち現在の生活様式を変える勇気が不足していることを意味します。
例:小説家を目指す人
ある人が小説家になることを夢見ていますが、忙しい日常生活が書く時間を制限しています。
結果として、作品を完成させたり、賞に応募することができません。
このような状況では、「応募してみなければ自分の可能性を保持できる」と考えがちです。
評価を受けること、そしてそれが否定的な結果に終わるかもしれないという恐れから、
実際には「もし時間がもっとあれば」とか「条件が整えば」と言い訳してしまいます。
「もし〜だったら」と常に条件をつけて考えている限り、本当の変化は起こりません。
アドラー心理学は、過去のどんな出来事も、これからの人生をどう生きるかに直接的な影響を与えないと教えています。
自分の人生の道筋は、過去や周囲の環境に依存するのではなく、現在、この瞬間に自分がどのような選択をするかによって決定されるのです。
第二夜 すべての悩みは対人関係
人間関係の悩み
アドラーは「人間のすべての悩みは対人関係に起因する」と主張しています。
- 私はお金持ちではない
- 私は身長が小さい
- 私には長所がない
これらは一見、対人関係とは無関係な悩みのように見えますが、実は異なります。
これらの悩みはすべて、他者との比較、つまりは対人関係の文脈で形成された「劣等感」に根ざしています。
劣等感は外部から強制されるものではなく、個人がどのように状況を解釈するかによって形成されます。
たとえば、「身長が小さい」という事実をコンプレックスと捉える代わりに、
それを「親しみやすさ」や「安心感を与える特性」として捉え直すことができます。
結局のところ、自己の特徴を長所として受け入れるか短所として捉えるかは、個々の解釈次第なのです。
劣等感と優越感の心理
劣等コンプレックスの影響
多くの人が「自分は他人より劣っているから、望むことができない」と考えます。
例えば、「他人に劣るから結婚できない」とか、「能力のない上司がいるから昇進できない」といった思考は、劣等コンプレックスの典型的な表れです。
このように感じる人々は、深層心理では成功を望んでおらず、現状から脱却することを恐れています。
変化に必要な勇気や努力を惜しむため、現状維持を選んでしまうのです。
優越コンプレックスの現れ
一方で、社会的ステータスのシンボルとして高級ブランドの服を着たり、高級車を目立つ場所に駐車する人々がいます。
また、過去の栄光を繰り返し語る人もいます。
これらの行動は優越コンプレックスの表れで、自身が他人より優れているという偽の感覚に浸ることで、内面の不安や劣等感をカバーしようとしています。
こうした人々はしばしば、自分を大きく見せるために権力や社会的地位を利用し、他者の価値観を模倣して生きているように見えます。
実際には、自らの本質的な価値を見失い、他人の認識に依存して自己価値を高めようと努力しています。
これらの心理状態は、自己受容の欠如と深く関連しており、真の自己実現への障壁となることが多いです。
対人関係の競争心理とその影響
競争を対人関係の中心に置くと、人々は永遠に人間関係の問題から解放されることがありません。
他の人が名門大学に進学したり、魅力的なパートナーと交際したり、裕福である事実を見て、
「自分はそれに比べてどうだろう?」と考えがちです。
このような比較は、しばしば劣等感を引き起こし、人々は自己価値を低く感じるようになります。
これを前向きな動機として利用できれば良いですが、多くの人はこれを劣等感や優越感の感情に変えてしまいます。
そして、他の人を「敵」と見なすようになり、競争心が強まることで人間関係が悪化します。
競争を心の中心から取り除けば、他人に勝つ必要がなくなり、他者を素直に祝福し、応援することができます。
この変化を実感することで、「すべての人が自分の味方である」と感じられるようになり、
対人関係のストレスが大きく減少します。この認識が、人間関係においてより健全で支え合える環境を作り出す鍵となります。